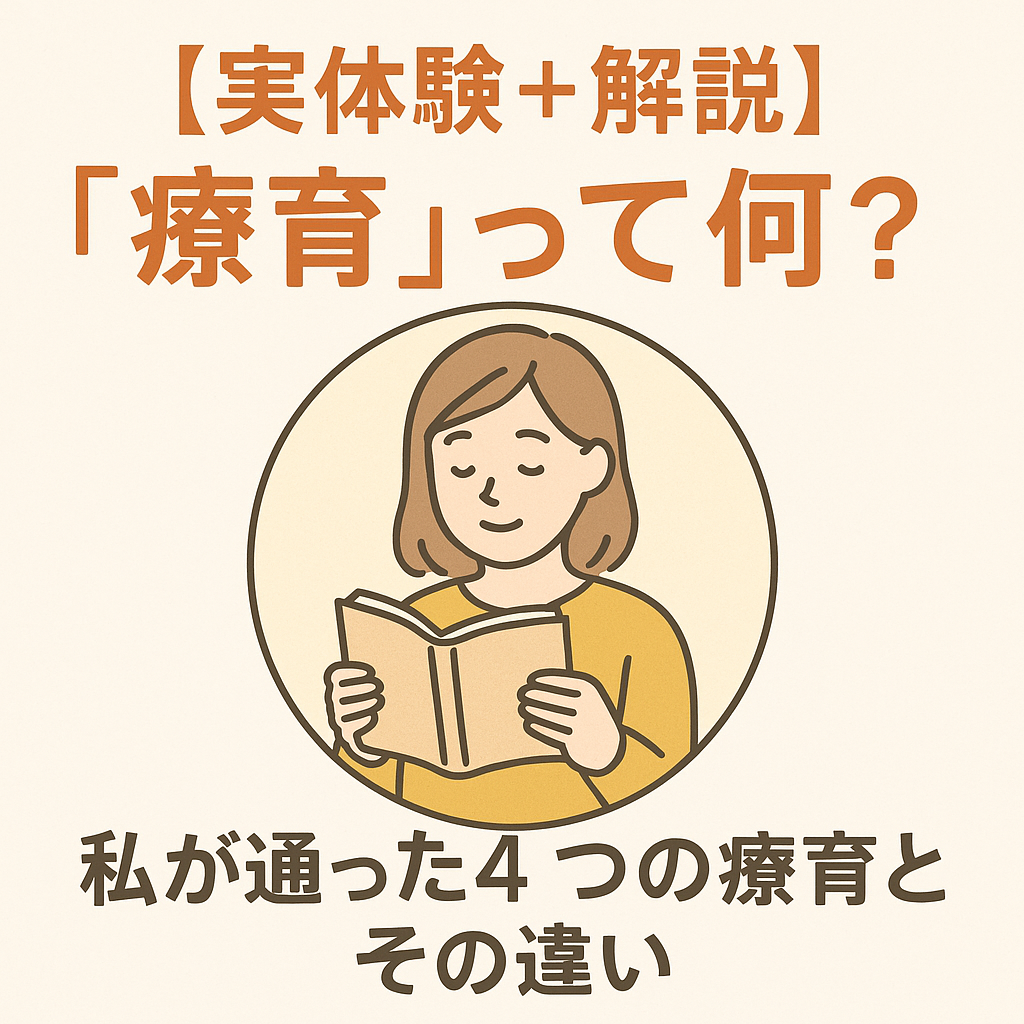
はじめに:「療育」って何だろう?
「療育って、どういう意味?」「うちの子にも必要なの?」
そんな疑問から、私はこの世界に入りました。
療育とは、発達に特性のある子どもが、自分らしく社会の中で成長していけるよう支援する取り組みです。
発達支援のプロ(保育士・作業療法士・言語聴覚士など)とともに、子どもの「できた!」を育てていく大切な時間。
でも実際には施設の種類も内容もさまざまで、「何を選べばいいの?」と悩む保護者も多いと思います。
ここでは、私が実際に体験した4つの療育の特徴と違いをまとめました。
実際に私が体験した4つの療育
① 療育園(通園型)
時間:10:00〜14:20(短時間)
他サービス併用:不可(単独利用)
休園日:土日祝日/GW・夏休み・年末年始
【特徴】
初年度は親子通園、2年目以降は年齢別クラスの単独通園に。
発達段階ごとにグループに分かれ、個別の目標に沿った支援。
行事が充実(夏祭り、運動会、お泊まり会、誕生日会など)。
保護者会・お父さん会など、親の参加・準備の負担が大きめ。
給食あり、先生は保育士中心で親が補助に入るスタイル。
●メリット:生活体験が豊富/社会性が育つ
●デメリット:親の関与が大きい/他施設との併用不可
② 児童発達支援(個別型)
時間:10:00〜11:40(約2時間)
形式:1対1のマンツーマン支援
併用:可能(曜日調整すればOK)
【特徴】
ST(言語)やOT(作業)など専門職が個別に支援。
苦手なことに集中して取り組める。
保護者が同席しない場合もあり、支援内容が見えにくいことも。
●メリット:集中して課題に取り組める/個別性が高い
●デメリット:報告が少なく、家庭でのフォローがしにくい
③ 児童発達支援(個別+集団型)
時間:10:30〜13:00(約2.5時間)
形式:前半=個別支援/後半=小集団(4人+先生1人)
併用:可能
【特徴】
ST・OTが個別支援に入り、苦手分野に的確に対応。
小集団活動で集団生活スキルや協調性を育む。
転倒リスクや個別配慮が必要な子にも柔軟に対応。
●メリット:個別と集団のバランスが良い/実生活に活きる
●デメリット:短時間なので十分な練習時間がとれないことも
④ 児童発達支援(集団型・外出支援あり)
時間:10:00〜15:30(長時間)
形式:集団活動中心、外出支援あり
併用:可能(曜日や枠次第)
【特徴】
小集団での療育をベースに、外出支援が豊富。
天気の良い日は近所の公園で自由遊び。
時には車で大きな遊具のある公園へ遠足のように連れて行ってくれる。
交通教室に参加し、実地で交通ルールを学ぶ機会もあり。
その日の活動内容は写真や動画付きでアプリを通じて保護者に報告され、安心感が高い。
●メリット:体を動かしながら社会経験が積める/活動内容が可視化される
●デメリット:集団なので個別対応はやや少なめ/長時間が負担な子もいる
療育を選ぶ際に確認すべきポイント
希望する時間に通えるか?
午前型・午後型・長時間型などさまざま
保育園と併用するなら時間の調整がカギ
子どもの疲れやすさ、生活リズムも考慮する必要あり
●送迎の有無
送迎ありの施設もあれば、完全に保護者任せのところも
自治体によっては「移動支援(ガイドヘルパー)」制度も利用可能(条件あり)
●他サービスとの併用が可能か?
よくある併用パターン(例)
曜日 午前 午後
月 保育園 個別療育
火 療育園(単独) 自宅
水 集団+外出療育 自宅
木 保育園 保育所訪問支援
金 自宅 個別療育 or 休養日
療育園は原則単独利用。児発系は曜日分けで併用可能。
支給量(日数)の上限や施設の空き状況により調整が必要。
●利用料金について(2025年時点)
児童発達支援や療育園など、通所療育は「障害児通所受給者証」があれば自治体の9割補助があり、月額上限金額内で利用可能です。
世帯年収 月額上限
約890万円未満 約4,600円
約890万円以上 約37,200円
非課税・生活保護世帯 無料
※別途:給食費・送迎加算・教材費などが発生する場合あり。
最後に:療育は「育てる場所」であり、「つながる場所」でもある
子どもが安心して過ごせる環境を見つけられることは、親として本当にありがたいことでした。
一方で、療育は親自身が孤立しないための場にもなります。先生や他の親とつながることで、子どもへの理解も深まり、自分も少しずつ前向きになれました。
療育施設は見学や体験が可能です。迷ったときは、まず「行ってみる」ことから始めてみてください。

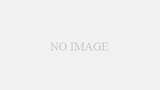
コメント